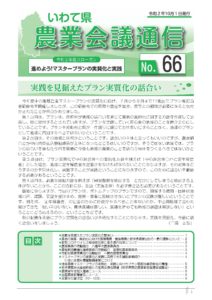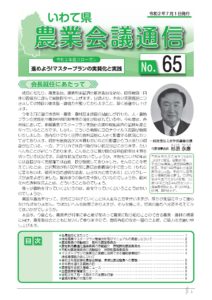照井会長の講話

ビジネスマナー研修の様子

農業機械の点検整備講習の様子1

農業機械の点検整備講習の様子2
岩手県農業法人協会は、会員法人が雇用する新採用(若手)社員・従業員のスキル向上のため、午前にジョブカフェいわてがビジネスマナーの合同研修を開催し、午後は株式会社西部開発農産による農業機械の点検整備講習を行いました。
参加者の感想は下記のとおり
1 法人協会会長の講話について
参加者の感想は下記のとおり
・今より効率よく早くやるにはどうしたら良いか考えながら仕事をするという話がそ
の通りだと思った
・将来、法人の社長を目指している。農業をする若い人達が少ないので自分から
進んで声掛けをして農業の体験をしてもらえるよう出来ればいい
・現在の農業の実情を知ることができた
2 社会人力向上セミナーについて
・ビジネスマナー等を今後の参考にしたい
・人とのコミュニケーションの大切さが理解できたので普段から積極的に交流し
ていきたい
3 農業機械の点検設備研修について
・オペレーターをする上でとても勉強になった
・当社には講師ができる整備士がいないのでとても参考になった
・点検、機械の不調の際に役立つ